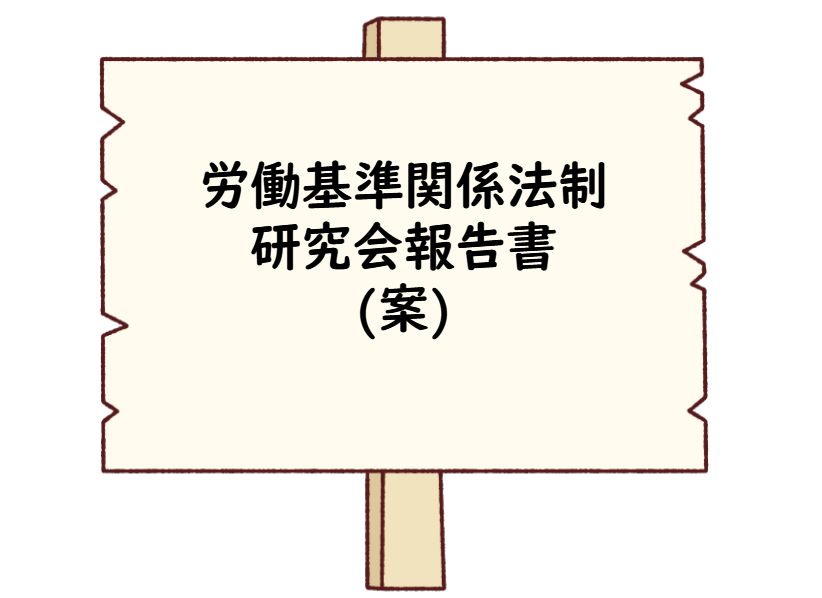はじめに
近年、働き方改革や技術革新により、私たちの働き方は大きく変化しています。副業や兼業が広がり、フリーランスやギグワーカーといった新しい働き方も登場しました。こうした変化に対応するため、労働基準法をはじめとする労働関係法制の見直しが求められています。
今回は、労働基準関係法制研究会報告書(案)をもとに、特に重要な3つのテーマについて考えていきたいと思います。
1. 副業・兼業における労働時間管理の簡素化
なぜ簡素化が必要なのか?
副業や兼業が一般的になる中で、複数の事業所で働く労働者の労働時間管理が複雑化しています。現行制度では、労働時間を通算して割増賃金を計算する必要があるため、企業側にとっては管理が煩雑になり、労働者側も自己申告の手間が増えるという課題がありました。
労働時間管理の簡素化に向けた動き
この状況を改善するため、報告書では以下のような方向性が示されています。
- 労働者の健康確保を大前提とした上で、割増賃金の支払いについて、労働時間の通算を必ずしも必要としないように制度を見直すこと
- 副業・兼業を行う労働者の健康確保を優先し、安全配慮義務を明確化すること
これにより、企業側の負担を軽減しつつ、労働者が安心して多様な働き方を選択できる環境づくりを目指しています。
用語解説
- 割増賃金: 法定労働時間を超える時間外労働や休日労働に対して支払われる通常の賃金に上乗せされた賃金のこと。
2. 労働者の健康管理責任の明確化
労働者の健康管理責任の重要性
労働者の健康は、労働生産性の維持、ひいては企業全体の成長に欠かせないものです。しかし、働き方が多様化する中で、企業による労働者の健康管理責任があいまいになっている側面もあります。
健康管理責任明確化の必要性
報告書では、労働時間や労働からの解放に関する様々な規制や制度について論じられていますが、これらと併せて、労働者の健康管理責任の明確化の必要性が訴えられています。
- 企業は、労働時間管理だけでなく、労働者の健康状態を把握し、必要な措置を講じる責任を負うべき
- 企業は、長時間労働や不規則な働き方による健康リスクを把握し、対策を講じる必要性がある
- 健康診断やストレスチェック等の制度を適切に運用するだけでなく、労働者自身が健康管理に主体的に取り組むことも重要である
用語解説
- 安全配慮義務: 労働者が安全に健康な状態で働けるように、企業が配慮する義務。
3. ギグワーカーやプラットフォームワーカーなどの新しい働き方への労働者性判断の明確化
新しい働き方の拡大と課題
近年、インターネットを通じて単発の仕事を請け負うギグワーカーや、プラットフォームサービスを提供するプラットフォームワーカーといった新しい働き方が拡大しています。しかし、これらの働き方は、従来の労働者の定義に当てはまらない場合が多く、労働法制による保護の対象となるかどうかが不明確でした。
労働者性判断の明確化に向けた動き
報告書では、これらの働き方を巡る課題に対し、以下の方向性が示されています。
- 労働者性を判断する基準を明確化し、実態として労働者に近い働き方をしている人を保護する
- 雇用契約という形式にとらわれず、実質的な働き方に基づいて判断すべき
- 労働者と非労働者の境界を明確化し、法制度の適用範囲を明確化する
- 労働者として保護されるべき人に対しては、労働基準法などの労働関係法規を適用する
この議論を通じて、新しい働き方をしている人も安心して働けるように、労働関係法制の適用をより柔軟に検討していくことが求められます。
用語解説
- ギグワーカー: インターネット上のプラットフォームを通じて、単発の仕事を請け負う働き方の人。
- プラットフォームワーカー: インターネット上のプラットフォームを通じて、サービスを提供する働き方の人。
まとめ
今回のブログ記事では、労働基準関係法制研究会報告書(案)をもとに、副業・兼業における労働時間管理の簡素化、労働者の健康管理責任の明確化、ギグワーカーやプラットフォームワーカーなどの新しい働き方への労働者性判断の明確化という3つのテーマについてご紹介しました。
これらのテーマは、これからの労働環境を考える上で非常に重要なものです。今後の法改正の動向を注視するとともに、私たち一人ひとりが、より良い働き方について考えていく必要があるでしょう。
最後に このブログ記事は、労働基準関係法制研究会報告書(案)の内容を基に作成しましたが、報告書の内容はあくまでも「案」であり、今後の議論や法改正によって変更される可能性があります。最新の情報については、厚生労働省等の公式サイトをご確認ください。
参考資料
厚生労働省:労働基準関係法制研究会報告書(案) ※PDF資料